国家一般職は、国家公務員の中でも採用数の多い区分で、日本や地方全体の政策の実行に携わる魅力的な仕事です。
一方で「国家一般職はやめとけ・つらいといった声が気になる」「具体的に何をする仕事か分からない」などの悩みを抱えている方もいるでしょう。
本記事では、元国家公務員の筆者が、国家一般職がやめとけといわれる理由や働くメリット、倍率・難易度、採用までの流れについて経験を交えて徹底解説します。
仕事の実態を知って後悔のない就職の判断ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。
\ 国家公務員として働くイメージができる /
国家一般職とは
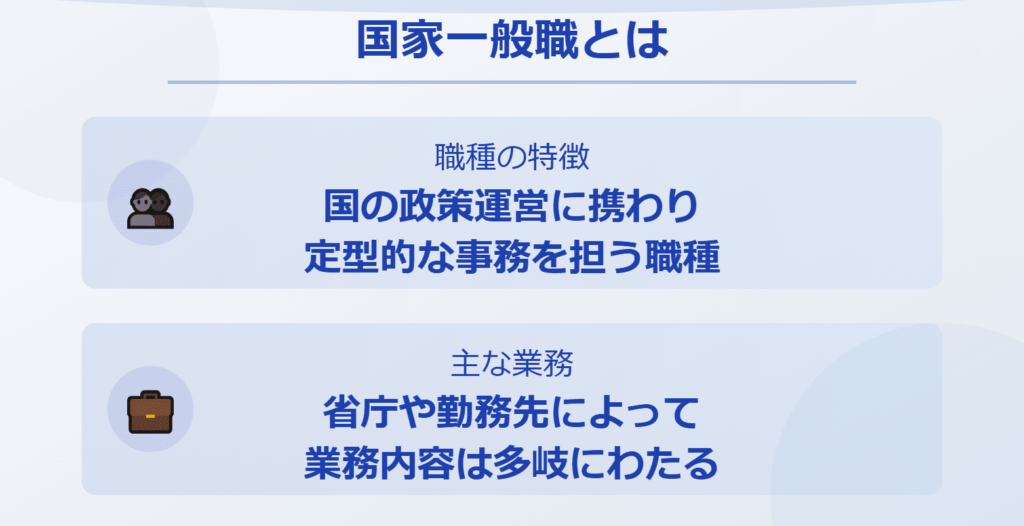
国家一般職とは、国の政策運営に携わる国家公務員のうち、主に定型的な事務を担う職種です。勤務先は霞ヶ関の本府省だけでなく、労働局や地方検察庁など全国各地にある出先機関が含まれます。
国家総合職が政策の企画・立案に取り組むのに対して、国家一般職は政策の実行や事務を担当することが特徴です。仕事内容は予算の執行・管理や政策立案に必要な調査、住民と関わる窓口業務など、多岐にわたります。
人事院の調査によると、行政職の国家公務員(総合職・一般職・専門職)のうち、国家一般職が全体の6割以上を占めており、まさに行政組織を支える屋台骨となっています。
また、最近では、これまで国家総合職が任されてきた役割を国家一般職の職員が担うケースもみられ、両者の違いは小さくなりつつあることも事実です。
国家一般職の仕事内容は省庁ごと、あるいは本府省・出先機関によって異なります。人事院の採用情報NAVIでは、各省庁の採用サイトがまとめられているので、チェックしてみましょう。
参照:人事院「令和5年度 年次報告書」
参照:人事院「国家公務員試験採用情報NAVI」
国家一般職はやめとけといわれる理由
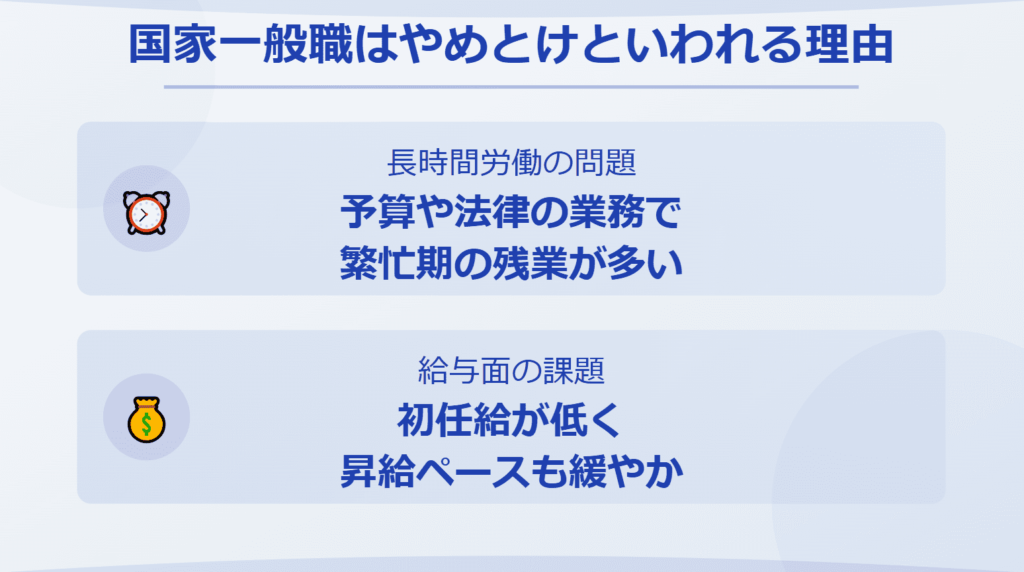
国家一般職は以下のような理由からやめとけといわれることがあります。
- 部署によっては残業が多い場合があるため
- 初任給が少なく給料の伸びも緩やかなため
- 仕事を通じて成長できる機会が少ない場合があるため
内閣官房の調査によると、20代~30代で国家公務員を離職したいと思っている職員のうち、長時間労働に不満がある職員が約3割、収入の低さへの不満を抱く職員が約4割いることがわかっています。
国家一般職はやりがいのある仕事ですが、働き方や待遇面で厳しい実態があることは否定できません。
それぞれについて、元国家公務員の視点から詳しく解説します。
参照:内閣官房「令和4年度職員アンケート調査結果」
部署によっては残業が多い場合があるため
配属先の部署によっては長時間残業が続く可能性があるため、国家一般職はやめとけといわれることがあります。
国家一般職の平均的な残業時間は、本府省と出先機関で大きく異なります。
令和6年度に人事院が公表した調査によると、本府省において予算や国会対応などの忙しい業務を抱える部署で働く職員3.8万人のうち、月100時間以上の残業をした職員が約14%、月平均80時間以上の残業をした職員が約19%です。一方、出先機関の場合は、そもそも多忙な部署に該当することがほとんどありません。
なお、本府省では、予算要求や国際会議の開催といった特定のプロジェクトが原因で一時的に忙しくなるケースが多く、仕事が一段落すれば残業は減ります。また、人事異動のタイミングで、次は落ち着いた部署に配属されるような配慮が行われやすいのも事実です。
自身が志望する省庁の職員の話を聞いて、激務の実態や傾向を把握しておくことをおすすめします。
参照:人事院「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等について」
初任給が少なく給料の伸びも緩やかなため
国家一般職は初任給が少なく基本給も年功序列で緩やかに伸びていくことも、やめとけといわれる理由の一つです。
例えば、国家一般職として出先機関に配属された場合、大卒の初任給は約22万円、高卒の初任給は約19万円です。年齢を重ねても給料の伸びが緩やかであり、大卒の30歳で約26万円、40歳でも約31万円にとどまります。なお、上記はあくまで残業代を含まない基本給なので、忙しい部署では給料が高くなる点に注意が必要です。
民間企業に就職した大学の同級生と比べると、給料の上限を物足りなく感じてしまう可能性があります。そのため、金銭面でまったく不自由なく生活したい方は、就職を慎重に検討するとよいでしょう。
ただし、国家一般職を含む国家公務員の給料は、景気に左右されない安定性があります。実際、コロナ禍で多くの企業が給料の減額を迫られる中、国家公務員の給料は1%以下の減額にとどまり、ボーナスも満額支給でした。
さらに、近年は若手を中心とした待遇改善が進んでいます。例えば、人事院の資料によると、令和6年には本府省の国家一般職(大卒)の初任給が月額約25万円から月額約27万円と、約2万円引き上げられました。
参照:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み(令和6年8月)」
仕事を通じて成長できる機会が少ない場合があるため
国家一般職は、部署によっては仕事が比較的単純で自己成長する実感が沸きにくいため、やめとけといわれることがあります。政策の企画・立案の仕事が中心である国家総合職の仕事と比較すると、能力の差が仕事の成果に比較的反映されにくい傾向があるのは事実です。
例えば、補助金の交付要綱を前例踏襲で作成する業務や、決まった手順に沿って調査を実施して集計する業務などが挙げられます。定型的な業務をする部署では、突発的な業務やトラブルが発生する機会も多くありません。
ただし、省庁や部署によっては、国家一般職が国会対応や省庁全体の調整業務といったチャレンジングな仕事を任されている場合も増えています。出先機関であれば、地方の事業や施策の企画といった規模の大きな仕事に携われる機会もあります。
入省後にイメージとのギャップを感じないよう、事前に説明会やOB訪問などの機会を積極的に活用しましょう。
\ 効率的に情報収集できる /
国家一般職として働くメリット
国家一般職として働く主なメリットには、以下の3つが挙げられます。
- 国全体の政策運営に携われる
- 特定の行政分野に長期間コミットしやすい
- 転勤を伴う異動の機会が少ない
元国家公務員である筆者の視点から、外からは見えにくい魅力について、具体的な経験を交えて説明します。
国全体の政策運営に携われる
国家一般職として働くメリットには、国や地方全体の政策運営に携われて、スケールの大きい仕事ができる点が挙げられます。
仕事のテーマには、社会保障や労働、地方創生、外交・防衛など、社会課題の解決に直結するものが多くあります。ニュースやSNSで日々話題になる重要な政策の一端に関われるのは、国家一般職ならではの醍醐味です。
また、国家一般職は国家総合職が決めたことをそのまま執行すると誤解されることもありますが、実態は異なります。国家総合職が決めるのは、あくまで大枠の方針です。個別の事業をどう設計するか、予算がどれくらい必要かなどの企画は、国家一般職の職員が裁量を発揮する場面が多くあります。
予算規模が大きく、多くの関係者が関わる仕事に携わりたい方には、国家一般職は魅力的な選択肢です。
特定の行政分野に長期間コミットしやすい
数年おきに部署の分野が大きく変わる国家総合職と異なり、特定の行政分野に長期間コミットしやすい点も国家一般職のメリットです。
地方の出先機関(労働局や法務局、税関など)に就職した場合、その分野に関係する仕事を何年も積み重ねることが一般的です。そのため、国家一般職の仕事を通じて、特定分野のスペシャリストになれます。
また、本府省では省庁や人事の方針によりますが、同じ分野の部署に配属され続ける可能性が総合職よりも高いことも特徴です。
一つの行政分野は年単位でじっくり担当してこそ、その魅力が見えてきます。業界の関係者や自治体ともつながりを作りつつ、その分野に精通した職員になれる国家一般職は、やりがいの大きい仕事です。
転勤を伴う異動の機会が少ない
国家一般職で働くメリットには、転勤を伴う異動や引っ越しの可能性が比較的少ないことも挙げられます。
出先機関に就職した場合は、基本的にその管轄内での部署異動が中心です。本府省の場合も、地方への転勤もある国家総合職と比べると、国家一般職は配属リスクが少ない傾向にあります。
転勤が少なく勤務地が予見しやすいことは、特に出産・子育て・介護などのライフステージに差しかかる職員にとって重要なポイントです。国家一般職は、国家公務員という安定したキャリアであり、人生設計を立てやすい点が魅力です。
なお、国家一般職でも地方の出先機関から本府省などへ出向する希望を出せるため、転勤がまったくできないわけでもありません。
国家一般職の採用試験の倍率・難易度
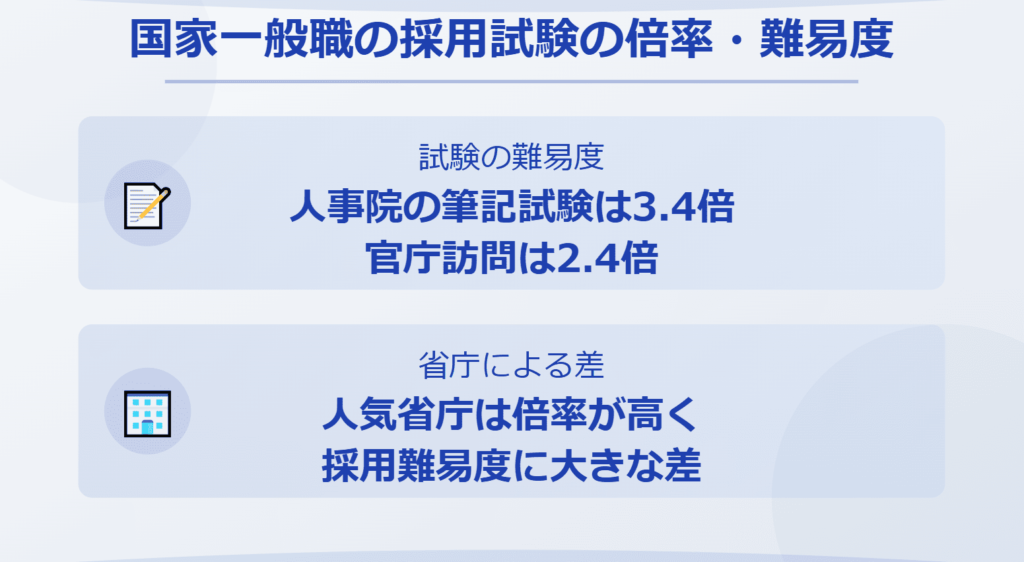
人事院の調査によると、国家一般職の大卒程度試験・高卒者試験について、人事院の試験の倍率は3.4倍、官庁訪問(各省庁による採用面接)の倍率は2.4倍です。全体としてみると国家一般職の倍率は一定の水準を保っており、採用の難易度はけっして低くないといえます。
採用試験に関する細かいデータは、以下の表のとおりです。
| 項目 | 大卒程度試験 | 高卒者試験 |
|---|---|---|
| 申込者数 | 28,103 | 11,191 |
| 合格者数 | 8,156 | 3,333 |
| 採用者数 | 3,446 | 1,399 |
| 試験倍率 | 3.4 | 3.4 |
| 採用倍率 | 2.4 | 2.4 |
上記のように、国家一般職の大卒程度試験・高卒者試験いずれも、倍率はほぼ揃えられています。
ただし、試験の倍率はあくまで各省庁全体の平均倍率であり、実際の採用難易度は省庁ごとに大きく異なります。例えば、例年人気がある労働局や法務局、経済産業局などは志望者が集中し、官庁訪問はさらに高倍率です。
各省庁ごとの倍率は細かく公表されていないため、数字で判断はできませんが、一般的に人気があるといわれる省庁は難易度が高い点は押さえておきましょう。
国家一般職に採用されるまでの流れ
国家一般職に採用されるまでの流れは、以下のとおりです。
- 説明会への参加やOB訪問を通じて志望省庁を決める
- 人事院主催の試験に合格する
- 官庁訪問を突破する
それぞれ詳しく解説します。
1.説明会への参加やOB訪問を通じて志望省庁を決める
国家一般職の採用に向けて、まずは説明会やインターンシップ、OB訪問などを通じて省庁の実態を理解した上で、志望先を絞る必要があります。志望省庁や目標が明確になれば、試験対策に集中して取り組め、面接対策も効果的に進められるためです。
各省庁のホームページやパンフレットによって、最低限の情報は集められます。一方、国家一般職の仕事に関するリアルな情報を集めるためには、職員や経験者による生の声を聞くことが大切です。
説明会やOB訪問を効果的に活用するコツには、以下が挙げられます。
- 説明会やインターンシップなどに参加する際は、どんな情報を得るために行くか目的意識を持つ
- 事前に公表資料を利用して基礎情報をしっかりインプットする
- 説明会で会った職員やOBにしか話せない個別具体的な質問をする
自分の足を使って得られた情報は、志望省庁の決定に役立つだけでなく、国家一般職の面接試験での志望動機として活用できます。
2.人事院主催の試験に合格する
国家一般職として受験する志望省庁が定まったら、人事院が主催する筆記試験に向けて準備をし、合格する必要があります。
国家一般職の範囲は、数的処理・文章理解などの基礎的な能力・知識に関する試験、法律・政治学の専門試験など多岐にわたります。合格のためには、試験に特化した勉強を着実に進めることが不可欠です。
一方で、人事院の試験はあくまで基礎的な事務処理能力の確認にすぎず、より重要なのは官庁訪問の面接です。そのため、試験対策は確実に合格点を取ることを目指して効率化する必要があります。
具体策な方法の例は、以下のとおりです。
- 本格的に対策を始める前に情報収集を徹底する
- 過去問をベースに、合格最低点を超える戦略を立てる
- 面接試験は評価基準を理解した上で、事前練習を積む
特に、地方の受験生などは情報収集の機会が乏しい場合、一定の費用はかかりますが、効率的な対策をするために公務員試験対策の予備校を利用することをおすすめします。
参照:人事院「一般職(大卒程度試験)受験案内」
参照:人事院「一般職(高卒者試験)受験案内)」
3.官庁訪問を突破する
人事院試験に合格しても、官庁訪問で志望先の省庁から内定をもらえなければ、国家一般職として採用されません。
筆記試験の対策はもちろんのこと、並行して省庁の研究や面接対策を進める必要があります。志望動機では、単に省庁の魅力を伝えるだけではなく、自らの経験と結びついた自分だけの想いを話すことが重要です。
また、官庁訪問では、その場での臨機応変な対応力も求められます。提示された議題に対して、すぐに論理的な意見を構築できるのは、公務員になってからも必須の力です。
評価ポイントにしっかりと対応できるよう、実績が豊富な予備校や省庁で働くOBなどに厳しくフィードバックしてもらいましょう。
【2025年最新】国家一般職の試験日程
2025年度の国家一般職・大卒程度試験の日程は、以下のとおりです。
| 受付期間 | 2月20日〜 3月25日 |
| 第1次試験日 | 6月1日 |
| 第1次試験合格者発表日 | 6月25日 |
| 第2次試験日 | 7月9日〜 7月25日 |
| 最終合格者発表日 | 8月12日 |
また、2025年度の国家一般職・高卒程度試験は、以下の日程で実施されます。
| 受付期間 | 6月13日~6月25日 |
| 第1次試験日 | 9月7日 |
| 第1次試験合格者発表日 | 10月9日 |
| 第2次試験日 | 10月15日〜 10月24日 |
| 最終合格者発表日 | 11月18日 |
特に、各試験を併願する際には面接や試験の日程が重なる可能性が高いため、緻密な日程の管理が必要です。官庁訪問の予約を含め、必ず人事院のホームページから最新情報を随時チェックして、ミスのないよう対応しましょう。
国家一般職に関する情報は、以下の人事院の公式Xでも発表されるため、フォローしておくことをおすすめします。
参照:人事院「国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)」
参照:人事院「国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)」
国家一般職への就職は幅広い視点から検討しよう
国家一般職は主に政策を実行する役割を担っており、さまざまな社会課題の解決に携われるやりがいのある仕事です。一方で「残業が多い」「低年収」といった否定的なイメージもあり、やめとけといわれることもあります。
しかし、国家一般職の仕事の実態は、省庁や部署によって大きく異なります。また、給料アップなどの待遇改善の動きも加速しているのが実態です。
本記事の内容や実際の職員の声をもとに、幅広い視点から国家一般職への就職を検討してみましょう。
なお、本記事の筆者は、国家公務員の面接シートの添削や面接対策などの相談サービスを実施しています。総合職との併願を検討されている方も含め、ぜひご活用ください。
\ 自分に合ったアドバイスを受けられる /
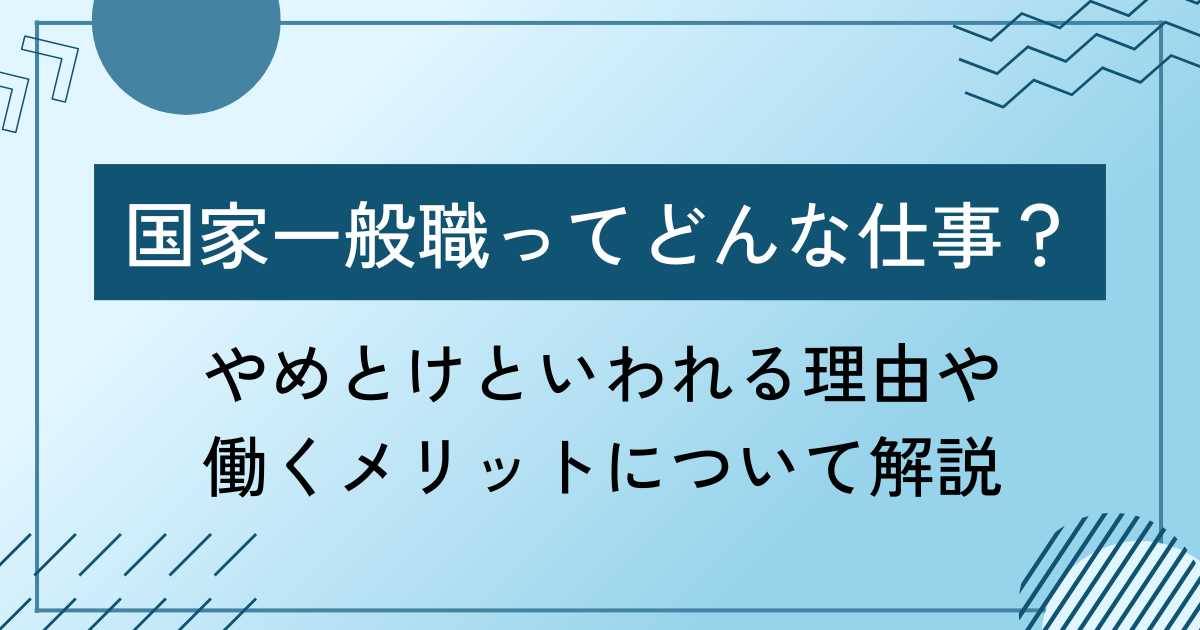
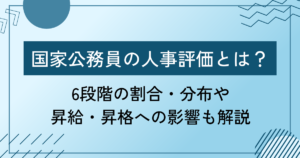
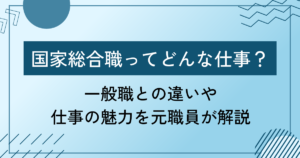
コメント