国家公務員の扶養手当について「いくらもらえるのか」「いつから廃止になるのか」といった疑問があり、簡単に調べたいと思っている方もいるでしょう。
国家公務員の扶養手当は、家族構成や収入状況により支給額や要件が細かく決まっており、変更点が多い制度のひとつです。配偶者手当の段階的廃止や子ども手当の増額が進むなかで、制度の全体像や今後の影響を押さえておくと、家計の見通しが立ちやすくなります。
本記事では、2026年時点の国家公務員の扶養手当の仕組みや支給額、支給要件、改正内容を整理し、損をしないためのポイントをわかりやすく解説します。
国家公務員の扶養手当とは

国家公務員の扶養手当とは、扶養親族を有する職員に対して支給される、生活支援を目的とした手当制度です。給与法第11条に基づき、扶養親族がいる職員へ毎月支給され、家族を養う負担を軽くする制度として設計されています。
扶養親族の範囲は人事院規則9-80で定められており、主な対象は以下のとおりです。
- 配偶者
- 一定年齢までの子や孫
- 60歳以上の父母や祖父母
- 一定年齢までの弟妹
- 重度心身障害者
いずれも他の収入手段が乏しく、主として国家公務員の収入で生活している家族が対象です。
国家公務員の扶養手当は、俸給や地域手当、管理職手当と並ぶ諸手当の一つとして扱われます。各府省では、人事院規則や通知に沿って事務を行われています。
近年は、配偶者手当を縮小し、子ども手当を手厚くする方向へ見直しが進んでいるのが大きな動きです。少子化対策や配偶者の就労促進を意識した制度へと変化しつつあると押さえておきましょう。
参照:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」
参照:e-Gov法令検索「人事院規則九―八〇(扶養手当)」
国家公務員の扶養手当の支給額
国家公務員の扶養手当の支給額は、家族の区分や職員の級によって異なります。2026年時点では、以下の金額での支給が基本です。
| 対象 | 金額 |
|---|---|
| 配偶者 | 月3,000円 |
| 子 | 月11,500円 |
| 16~22歳の子 | 月11,500円に5,000円を加算 |
| 父母等 | 月6,500円 |
行政職俸給表(一)の8級以上の職員には、配偶者手当が支給されません。父母等に対する手当も月3,500円に抑えられ、9級以上の職員には支給されない決まりです。
また、16歳から22歳までの子に対する加算は、学費や仕送りなど教育費の負担を意識した設計です。高校から大学・専門学校までの時期に多くかかる支出を補う狙いがあります。
金額の改定は、給与制度全体の見直しと連動します。俸給や地域手当と同じタイミングで扶養手当も調整され、給与制度のアップデートの一要素として位置付けられています。
なお、給与明細上では、俸給・地域手当・管理職手当などと並び、扶養手当が一つの欄で表示されます。家族構成が変わると、月々の手取りが数千円から1万円前後変化する場合もあるため、金額と条件の確認が欠かせません。
参照:人事院「国家公務員の諸手当の概要」
国家公務員の扶養手当の支給要件
国家公務員の扶養手当を受けるには、職員に扶養親族がいる必要があります。
扶養親族の範囲や要件は、給与法第11条と人事院規則9-80で定められており、主な項目は以下のとおりです。
- 主として国家公務員の収入で生活している家族である
- 年間収入の見込みが原則130万円未満である
- 他の扶養義務者による家族手当の対象になっていない
支給要件は、家族の属性ごとに細かく分かれます。配偶者や子ども、親族などの区分ごとの条件を以下の見出しで確認しましょう。
参照:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」
参照:e-Gov法令検索「人事院規則九―八〇(扶養手当)」
配偶者手当の支給要件
配偶者が扶養手当の対象となるには、他に扶養手当を受ける扶養者が存在せず、主として国家公務員本人の収入で生活していると認められる必要があります。行政職8級以上の職員には原則として不支給です。
所得面では、配偶者の年間収入見込みが原則130万円未満である点が条件です。
共働きの家庭で配偶者が育児休業中の場合、育休給付金などを含めた年収が130万円未満であれば、一時的に扶養手当の対象になります。復職後に収入が増えれば対象から外れるため、その都度見直しが必要です。
なお、配偶者に対する扶養手当は、法律上の配偶者だけでなく、婚姻に近い実態を持つ内縁関係も対象となりえます。
子ども手当の支給要件
国家公務員の扶養手当における「子」は、満22歳に達した後、最初の3月31日までの期間にある子です。大学や専門学校へ進学した場合も、22歳年度末までは年齢要件を満たします。
子どもに自分で生計を維持できる収入がなく、主として国家公務員である親の収入で生活している場合が対象です。対象となる子の人数分だけ扶養手当を受給でき、多子世帯ほど合計額が大きくなります。
また、高校から大学等への進学期にある子には、通常の子ども手当に加えて月5,000円の加算が設けられます。15歳到達後の4月1日から22歳年度末までが目安です。
共働き世帯では、どちらの親が子どもを扶養親族として届け出るかを決める必要があります。一般に収入水準や勤務先の扶養手当の有無を比較し、主たる扶養者を選びます。
離婚や別居により子どもと同居していない場合も、仕送りや学費負担などを通じて生活費の大部分を負担していれば扶養手当の対象です。
親族手当の支給要件
親族に対する扶養手当の対象には、60歳以上の父母や祖父母、22歳年度末までの孫や弟妹、重度心身障害者などが含まれます。行政職8級以上の職員に対する父母等の扶養手当は、8級で月3,500円、9級以上は不支給です。
これらの親族も、「他に生計の道がなく主として職員の扶養を受けている」という条件が前提です。
父母などについては、配偶者や兄弟姉妹など扶養しうる立場の家族が存在するかどうかを戸籍や所得証明で確認します。国家公務員以外に十分扶養できる者がいれば、原則として扶養親族に含めない運用です。
就業中の親族は、勤務条件や賞与の有無を含めて年収見込みをチェックし、130万円を超えないかどうかで判断します。親族がすでに別の公務員や事業所で家族手当の対象になっている場合、国家公務員の扶養手当の対象外です。
別居している扶養親族の支給要件
別居している家族でも、国家公務員が実質的に生活費を負担している場合、扶養親族として認定される可能性があります。別居の扶養親族について、職員が主として扶養しているかどうかを扶養親族届や認定簿などに基づき判断される仕組みです。
具体的には、国家公務員側が生計費の3分の1以上を送金し、金融機関を通じた定期的な振込が続いている場合には、扶養親族として認定されます。
特に進学のため下宿している子どもは典型例です。仕送りや学費負担によって国家公務員が生計を維持していると認められれば、扶養親族として扱われます。
国家公務員の扶養手当の改正内容
2024年の人事院勧告では、国家公務員の配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当を1人当たり月13,000円に引き上げる方針が示されました。
背景には、配偶者に家族手当を支給する企業の減少や、公務職場で配偶者を扶養する職員の割合が低下している現状があります。また、配偶者手当が女性パートタイム労働者の「年収の壁」を生み、就業調整を誘発しやすい点も課題のひとつです。
国家公務員の扶養手当の改正スケジュールは、以下のとおりです。
- 令和7年度:配偶者手当を一部減額、子ども手当を月11,500円へ引上げ
- 令和8年度:配偶者手当を廃止、子ども手当を月13,000円へ引上げ
それぞれ詳しくみていきましょう。
参照:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」
配偶者手当が段階的に廃止される
2024年の人事院勧告では、国家公務員の配偶者に対する扶養手当を廃止し、その原資を子ども向けに振り向ける方針が打ち出されました。移行期間として2年間の経過措置を設ける形です。
行政職7級以下の職員に支給される配偶者手当は、以下のように段階的に縮小されます。
- 令和6年度:月6,500円
- 令和7年度:月3,000円
- 令和8年度:廃止(0円)
行政職8級以上の職員などに支給される配偶者手当は、令和7年度で廃止されました。管理職相当の層では、早い段階で配偶者手当がなくなる設計です。
見直しの背景には、配偶者の年収要件付き手当が年収の壁を作り、特に女性パートの就業調整を招くとの指摘があります。民間企業でも配偶者手当を縮小し、子ども手当へシフトする動きが進んでおり、国家公務員の制度もその流れに合わせた形です。
子ども手当が増額される
人事院勧告では、国家公務員の配偶者手当の廃止とセットで、子に係る扶養手当を1人当たり月13,000円へ引き上げる方針が示されました。こちらも2年間で段階的に実施されます。
子ども手当の水準は、以下のように段階的に縮小される予定です。
- 令和6年度:月10,000円
- 令和7年度:月11,500円
- 令和8年度:月13,000円
増額の理由として、子どもに要する教育費や生活費の実情、国として進める少子化対策、子どもを持つ職員の生活費補填の必要性が挙げられています。
改正後は、配偶者の有無より子どもの有無によって扶養手当額が決まる色合いが強まります。国家公務員の扶養手当が、より子育て世帯へ重点配分される制度へ変わる流れといえます。
国家公務員の扶養手当の申請方法
国家公務員が扶養手当を受給するには、まず扶養親族届を提出し、所属庁の長から扶養親族として認定を受ける必要があります。様式は人事院が定める統一様式が基本で、初回の申請だけでなく、その後の家族構成や収入状況の変化も届出の対象です。
基本的には所属省庁の案内に従えば問題ありませんが、事前に以下の見出しで詳細を簡単に確認しておくと、手続きをスムーズに進められます。
扶養手当申請に必要な書類がある
扶養親族届では、扶養親族の氏名や続柄、生年月日、同居か別居か、所得状況などを記入します。あわせて内容を裏付ける書類を添付する必要があり、公的書類と収入関係書類を組み合わせて提出します。
主な書類の組み合わせは以下の表のとおりです。
| ケース | 主な提出書類の例 |
|---|---|
| 収入がある扶養親族の年間収入見込み(130万円未満かの確認) | 所得(課税)証明書、給与支払証明書、源泉徴収票 |
| 年金受給者を扶養に入れる場合の年金額・所得確認 | 年金証書、年金改定通知書、課税(所得)証明書 |
| 学生の子ども・孫の学生要件・年齢要件の確認 | 在学証明書、学生証の写し |
| 別居している扶養親族の仕送り実績・生計維持の確認 | 振込明細書、通帳の写し(直近3か月分など) |
| 育児休業中の配偶者の収入見込み(年収130万円未満かの確認) | 育児休業開始通知、育児休業給付金の決定通知 |
| 重度心身障害者の障害程度・認定内容の確認 | 医師の証明書、障害者手帳の写し |
実際に必要な書類は、人事課や会計の担当者に確認しましょう。
扶養状況の変更時に手続きを行う
国家公務員の扶養手当は、一度申請して終わりになる制度ではありません。状況が変わるたびに扶養親族届を提出し、認定される内容を更新する必要があります。
多くの府省では、変更届の提出期限を「事実発生日から15日以内」などと定めています。職員自身が扶養状況の変化を把握し、速やかに申告する姿勢が求められます。
代表的な変更場面の例は次のとおりです。
- 子どもの就職や独立
- 配偶者の収入増加や転職
- 親族の年金受給開始や就労開始
各庁の長は、少なくとも年1回、扶養親族が要件を満たしているかどうかを職員に確認します。扶養手当は家族の状況に合わせて継続的に調整される制度のため、家族構成や収入に変化があった場合は、早めの届出を意識することが重要です。
国家公務員の扶養手当の制度を理解して家計の計画を立てよう
国家公務員の扶養手当は、扶養親族の有無や区分、収入状況で支給額が変わる家族手当であり、毎月の手取りに直接影響します。配偶者手当の段階的な廃止や子ども手当の増額スケジュールを把握すれば、数年先までの収入見通しを具体的に描きやすくなります。
扶養親族届の提出タイミングや必要書類、変更時の届出ルールを押さえることで、過払い・受け取り漏れのリスクも抑えられます。家族構成や働き方が変わる局面では、その都度人事担当や共済組合に相談し、扶養手当の扱いを確認しながら中長期の家計プランを組み立てましょう。

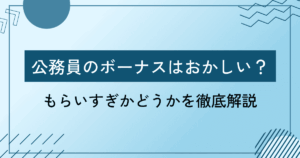
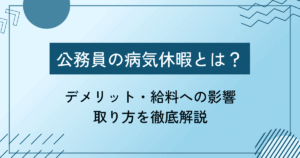

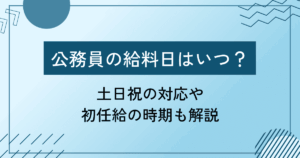
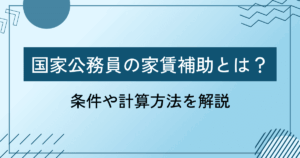
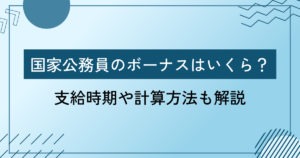
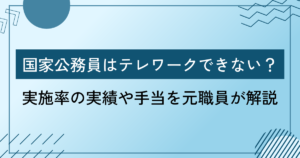
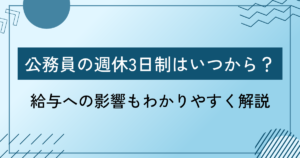
コメント